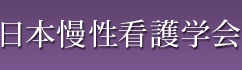論文投稿について
論文オンライン投稿について
2019年10月から日本慢性看護学会では、論文投稿の電子化を行うこととしました。
これに伴い、論文投稿・査読はガリレオ社の提供するオンライン投稿・査読システムへ移行することとなりました。
オンライン投稿手順については 「日本慢性看護学会 学会誌オンライン投稿手順」(PDF)をご参照ください。
オンライン投稿手続きは論文の筆頭者である会員が行ってください。この際、当年度の会費を完納していない場合は「投稿資格なし」とされますので、速やかに年会費の納付を行ってください(年会費の納付から入金処理の完了までには1週間ほどの処理期間がございますので、ご了承ください)。
投稿原稿の作成、準備に際しては下記の投稿規定を熟読いただき、原稿、図表および必要書類をご用意の上、オンライン投稿システムへアップロードください。なお、必要書類については、下記より書式をダウンロードしてください。
利益相反(COI)申告書は研究者ごとに1枚、全員分のものを提出してください。
投稿規定
日本慢性看護学会誌 投稿規定
- 投稿者の資格
- 筆頭著者は本学会員(賛助会員を除く)とする.筆頭著者以外の著者には非会員を含めることができるが,非会員の場合には,採択後に掲載料を支払う必要がある.但し,編集委員会から依頼された原稿についてはこの限りではない.
- 原稿の種類
- 1)原稿の種類は,論壇,総説,原著論文,研究報告,実践報告,資料,その他であり,それぞれの内容は下記のとおりである.
【論壇】 慢性看護学に関わる問題や話題のうち,議論が交されつつあるものについて今後の方向性を指し示すような著述や提言. 【総説】 慢性看護学に関わる特定のテーマについて多面的に内外の知見を集め,また文献等をレビューして,当該テーマについて総合的に学問的状況を概説し,考察したもの. 【原著論文】 研究論文のうち,研究そのものが独創的で,新しい知見や理解が論理的に示されており,慢性看護学の知識として意義が明らかであるもの. 【研究報告】 内容的に原著論文には及ばないが,結果の意義が大きく,慢性看護学の発展に寄与すると認められるもの. 【実践報告】 慢性看護学の発展に寄与すると考えられる実践の内容を広く公開し、共有することの意義が明確に述べられているもの. 【資料】 慢性看護学および慢性看護実践の発展に寄与すると考えられる資料的価値があるもの.プロトコールの作成など. 【その他】 慢性看護学あるいは看護学の研究に関する見解等で,編集委員会が適当と認めたもの. - 2)投稿論文の内容は,他の出版物(国の内外を問わず)にすでに発表あるいは投稿されていないものに限る.重複投稿は禁止する.
- 1)原稿の種類は,論壇,総説,原著論文,研究報告,実践報告,資料,その他であり,それぞれの内容は下記のとおりである.
- 倫理的配慮
- 人および動物が対象である研究は,倫理的に配慮され,投稿者所属の施設の倫理委員会の承認を得ていることを,承認番号とともに本文中に明記する.
- 謝辞(あるいは助成等)
- 当該研究の遂行に関して受けた研究助成がある場合には,論文の末尾(文献の前)に「謝辞」の欄を設け,助成機関名とその旨を記載する.また,委員会活動の成果である場合は,その旨を記載する。著者以外で当該研究の遂行や論文作成に貢献した者がいる場合は,「謝辞」の欄に貢献内容を記して謝意を述べる.資金の獲得,データ収集,または研究グループへの部分的な助言のみを行った者などは著者にはあたらず,貢献した者に該当する.
- 利益相反
- 当該研究の遂行や論文作成において,利益相反となるような経済的支援を受けた場合や個人的利害関係が生じるような状態の場合には,その旨を「謝辞」の欄の次に,「利益相反」の欄を設けて記載する.また,利益相反状態が存在しない場合には,「本研究における利益相反は存在しない」と記載する.
- 投稿手続
- 1)論文の投稿は電子投稿システムで行う.
- 2)電子投稿システムに沿って,必要事項を入力する.
- 3)「原稿執筆要領」に沿って作成した原稿(PDFファイル),図表ファイル(PDF,画像ファイル)とともに,下記の書類(スキャンの上、PDFファイル化したもの)を電子投稿システムにアップロードする.
(1)著者誓約書(様式10) (2)投稿論文チェックリスト(様式11) (3)利益相反申告書
- 原稿の受付および採否
- 1) 投稿原稿の受付日は,電子投稿システムに投稿された日とする.ただし投稿規定および原稿執筆要領に従っていないものは受付けないことがある.
- 2)原稿の採否は査読を経て編集委員会が決定する.
- 3)編集委員会の判定により,原稿の修正および原稿の種類の変更を著者に求めることがある.
- 投稿された論文は理由の如何を問わず返却しない.
- 著者校正
- 査読を経て,編集委員会に受理された投稿原稿については,著者校正は1回のみとする.但し,校正の際の加筆は原則として認めない.
- 原稿執筆要領
- 1)原稿は原則として,ワードプロセッサーで作成する.
- 2)原稿はA4版横書きで,1行の文字数を35字,1ページの行数を28行とし,適切な行間をあける.本文の文字の大きさは,10.5ポイントを使用する.また,行番号をページごと振り直してつける.
- 3)投稿原稿の1編は本文を下記の文字数以内とする.図表は,大きさにかかわらず文字数には含めず,投稿原稿1編につき所収する図表の数は,あわせて6点までとする.
論 壇 : 16,000字以内 総 説 : 16,000字以内 原著論文 : 16,000字以内 研究報告 : 16,000字以内 実践報告 : 16,000字以内 資 料 : 16,000字以内 その他 : 16,000字以内 - 4)外国語はカタカナで,外国人,日本語訳が定着していない学術用語などは原則として活字体の原綴で書く.
- 5)図,表
- (1)図,表および写真は,図1,表1,写真1等の通し番号をつけ,1ページに1点として作成する.
- (2)本文とは別に一括してファイル(PDFもしくは画像ファイル)にまとめ, アップロードする.
- (3)図は原則として白黒で作成する.グラフは,縦・横軸のラベル,縦軸の数値の単位などを記入する.図・写真のキャプション配置位置は,注記を含まない場合には図・写真等の本体の下側,注記を含む場合には図・写真等の上側に配置する.
- (4)表は原則として横罫線のみで表示し,縦罫線は表示しない.縦罫線のかわりに十分な空白を置く.数字は正,負 の数に関わらず,同列内の小数点の位置,小数点以下の桁数(有効数字に応じて)揃える.表中の数字が理論的に必ず1以下になる場合(相関係数など)は,0を付けずに「.82」のように小数点以下のみで記載する.表のキャプション配置位置は,表の上側とする.
- (5)本文原稿右欄外にそれぞれの挿入希望位置を朱書きする.
- 6)文献の記載方法は以下に従う.
- (1)使用した文献を本文中の適切な位置に挿入する.
- ①単独の著者
- 著者の姓と発行年を括弧表示する.
<例>
- 東京 (2006 ) の報告では, ….
- …ストレスが認められた (兵庫, 1996) .
- ②複数の著者
- 初出から,筆頭著者の姓に続けて「~ら」とし,欧文では「et al.」を記す.
<例>
- 東京ら (2006) は, ….
- Labkin et al. (2000) のストレスマネジメントでは,….
- …を占めた (日本ら, 2003).
- …ストレスが認められた (Labkin et al., 1998).
- ③翻訳書
- 原著者の姓と発行年/訳者の姓と翻訳書の発行年を表示する.
<例>
- …が認められる(Larson,1996/静岡,2010).
- Larson(1996/静岡,2010)によると,….
- ④複数文献の引用
- 複数の文献を引用した場合には,筆頭著者のアルファベット順に表示する.
<例>
- …が示されている(福岡, 2012; 東京, 2009).
- ⑤同一著者による,同じ年に発行された異なる文献
- 発行年にアルファベットを付して,文献を区別する.
<例>
- 岡山(2010a)によると,….また,…であることが明らかにされている(岡山,2010b).
- ⑥直接引用
- 直接引用の際には文献の該当ページを記載する.
<例>
- 東京(2010)は「慢性疾患は …である」(p201)と定義している。
- “In the United State, Heart failure patients ….”(Miller et al.,2010,p200)
- (2)引用文献リストは,筆頭著者の姓とイニシャルによってアルファベット順に列記する.
- *著者名は,筆頭著者名以下3名までを記載し,4名以上の場合は,「他」ないし「et al.」とする.
- *2行目以下は字下げ(2文字)をする.
- *英語文献の場合は,書名,論文名については最初の語,コロンやダッシュの直後の語,および固有名詞のみ語頭の文字を大文字で表す(それ以外の文字は小文字を使用).
- ①雑誌掲載論文:
- 著者名 (発行年) : 論文の表題, 掲載雑誌名, 巻 (号), 最初のページ-最終のページ.
<例>
- 兵庫太郎, 関東吾郎, 関西梅子, 他 (2007) : 慢性看護の現状, 日本慢性看護学会, 1(3), 1-10.
- Saywitz,A., Cohen,B., Kandel,C., et al. (2002) : Stress and Nursing, Journal of Japanese Society for Chronic Illness and Conditions Nursing, 1 (3), 1-15.
- Evans, A.D., & Tevlin, F. D.(2010) : The emerging study of midlife: Psychological and social development in middle age, Journal of Nursing Society, 6(3), 21-28.
- ②単行本:
- 著者名 (発行年) : 書名 (版数) , 引用箇所の最初のページ-最終のページ, 出版社名, 出版地.
- 著者名 (発行年) : 論文の表題, 編者名(編), 書名 (版数) , ページ数, 出版社名, 発行地.
<例>
- 慢性花子 (2005) : 呼吸器疾患看護 第2版, 25-28, 医学研究書房, 東京.
- 日本吾郎 (2004) : 睡眠障害と看護, 兵庫花子, 看護京子 (編), 臨床看護総論Ⅰ, 124, 医学研究書房, 東京.
- ③翻訳書:
- 原著者名 (原書の発行年) / 訳者名 (翻訳書の発行年) 訳 : 翻訳書の書名 (版数), 引用箇所の最初のページ-最終のページ, 出版社名, 発行地.
<例>
- Cabading, K. (2000) / 慢性京子 (2003) 訳 : 慢性病のストレス 第2版, 56-58, 医学研究書房, 東京.
- ④オンライン版でDOI(Digital Object Identifier,デジタルオブジェクト識別子)のない場合:
- 著者名(年号):論文の表題,収載誌名,巻(号),最初のページ-最終のページ,URL
<例>
- 秋田次郎, 東北花子, 関東松美, 他 (2014) : 慢性看護における体験の意味, 日本慢性看護学会, 9(3), 20-28, http://jscicn.com/magazine/contribution.html
- ⑤オンライン版でDOIのある場合:
- 著者名(年号):論文の表題,収載誌名,巻(号),最初のページ-最終のページ.doi: DOI番号
<例>
- 福井康二 (2014) : 看護実践の効果, 日本慢性看護学会, 10(3), 1-10. doi:10.1508
- ⑥Web ページなど,逐次的な更新が前提となっているコンテンツ,文書:
- 著者 : タイトル, 入手日, アドレス
<例>
- 日本慢性看護学会 : ABCDマニュアル, 2007-12-20, http://www.abcd.org/journl/manual.html
- (1)使用した文献を本文中の適切な位置に挿入する.
- 7)原稿には表紙を付し,上半分には表題,英文表題(主要語の語頭を大文字とする.接続詞,冠詞,短い前置詞は主要語とみなされない),図,表および写真等の数を書き,キーワードを日本語・英語でそれぞれ3語程度記載する.下半分には赤字で希望する原稿の種類,別刷必要部数,編集委員会への連絡事項などを付記する.
表紙には,著者名や所属機関名を記載せず,電子投稿システム画面上に著者名,所属機関名は入力する.投稿時にアップロードする本文原稿中には,受審した倫理審査委員会名・承認番号,謝辞における著者や所属機関を類推させるような情報は記載せず,伏字にする.なお,著者の既報論文は伏字にする必要はない.著者が特定されないように通常の第三者的な記載にする.
原稿の本文にはページ番号を付す. - 8)総説,原著,研究報告を希望の場合には,250 words前後の英文抄録ならびに400字程度の和文抄録をつける.和文抄録,英文抄録はそれぞれ改ページをし,表題と本文を記載する.抄録には,目的(Objective),方法(Methods),結果(Results),結論(Conclusions)を含める.英文抄録は,ダブルスペースで記載する.
- 9)論壇,実践報告,資料,その他を希望の場合は,400字程度の和文抄録をつける.抄録は改ページをし,表題と本文を記載する.抄録には,目的,方法,結果,結論を含める.
- 著作権
- 著作権は本学会に帰属する.掲載後は本学会の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる.最終原稿提出時,編集委員会より提示される著作権譲渡同意書に筆頭著者が自筆署名し,PDF ファイルを電子投稿システムにアップロードすること.
- 著者が負担すべき費用
- 1)掲載料 筆頭者および共著者全員が学会員の場合は無料とする.共著者に非会員が含まれている場合には,非会員 1 名につき5,000 円の掲載料を採択後に支払う.なお,掲載料はいかなる場合にも返金しない.
- 2)別刷料 別刷は全て実費を著者負担とする.
- 3)その他 図表等,印刷上,特別な費用を必要とした場合は著者負担とする.
- 附 則
- この規定は,2007年3月21日から施行する.
この規定の改正は,2007年6月10日から施行する.
この規定の改正は,2008年10月10日から施行する.
この規定の改正は,2009年11月14日から施行する.
この規定の改正は,2011年10月21日から施行する.
この規定の改正は,2013年5月11日から施行する.
この規定の改正は,2013年10月27日から施行する.
この規定の改正は,2014年10月26日から施行する.
この規定の改正は,2017年10月29日から施行する.
この規定の改正は,2018年5月20日から施行する.
この規定の改正は,2019年9月1日から施行する.
この規定の改正は,2020年6月26日から施行する.
この規定の改正は,2021年3月14日から施行する.
この規定の改正は,2022年11月13日から施行する.
この規定の改正は,2023年6月4日から施行する.
投稿者の皆さまへ
日本慢性看護学会誌編集委員会では、投稿論文が速やかに掲載されるように改善策について検討しております。
投稿者の皆さまは、投稿規定および学会誌オンライン投稿手順等をご確認頂き、不備がないようにご準備の上、オンライン投稿システムにて投稿頂けますようお願いいたします。また、以下のような場合には、下記編集事務局まで、ご連絡ください。
- 査読結果は、約2か月で返却出来るよう努めております。投稿後2か月を過ぎても連絡がない場合には、下記編集事務局まで、お問い合わせください。
問い合わせ先:日本慢性看護学会会員管理事務局(学会誌投稿・査読担当)
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2 大住ビル401
(株)ガリレオ学会業務情報化センター内
日本慢性看護学会会員管理事務局(学会誌投稿・査読担当)
FAX 03-5981-9852
E-mail: g046jscicn-editorial@ml.gakkai.ne.jp
査読結果に対する著者校正時の注意事項
- 改訂原稿は,オンライン投稿システムより、アップロードしてください。
- 査読者の意見に対しての回答書を作成し,オンライン投稿システムよりアップロードしてください。また,修正する場合は該当するページ数と行数を示し,査読者と意見の異なる場合は,その旨を詳しく記載してください。(具体的な修正方法については,下記の回答書例,もしくは学会誌11巻2号, pp. 112-113を参照)
- 査読コメントに対する本文中の修正箇所には,下線を引いてください。校閲のコメント機能は使用しないでください。
- 改訂原稿の返送が8週間を過ぎますと,新規投稿扱いになる場合がありますので,ご留意ください。
出典:田中真琴,柴山大賀,本庄恵子,他(2017):慢性看護学会誌編集委員会企画セミナー報告 慢性看護学の知の創出への道:学会発表から論文掲載へ, 日本慢性看護学会誌,11(2),112より引用、一部改変
-研究者としての研究倫理(研究および公表の公正さ)-
二重投稿についての注意
近年,同じ内容の論文を2種類の雑誌に投稿することが問題となっている.日本慢性看護学会編集委員会としては,以前に公表されたものまたは現在投稿中の類似した論文と比較して,以下のすべてに該当する内容の論文を二重投稿とみなして採用しない.
- 対象が基本的に同じであること
- 方法が同じであること
- 結果・考察に新しいものがないこと
また,以下の点も掲載の採否の参考とする.
- 既報の論文と比較し,読者に新しい情報が与えられないこと
- 既報の論文を故意に引用していないこと
ただし,学術集会などの抄録集,講演集は,該当しないものとする.掲載後に判明した二重投稿に対しては,その論文の撤回の旨を日本慢性看護学会誌に掲載することとする.
著者は,論文投稿に際し,本学会所定の「投稿論文チェックリスト」「著者誓約書」に必要 事項を記載し,各1部を提出する.
(上記内容は,日本超音波医学会ホームページをもとに一部修正をしたものである)
http://www.jsum.or.jp/manuscript/double.html
- 参考文献
- Repetitive publication. J Clin Ultrasound. 1989;17: 551.
Pitkin RM: Repetitive publication. Obstet Gynecol 1988; 72: 263-4.
なお,二重投稿と判断された会員(共著者を含む)には,本学会の学会誌への投稿および学術集会での発表を2年間認めない.
*機関リポジトリで全文公開されている論文は、すでに発表されているものとみなす。
投稿の取り下げに対する注意
原稿の査読のプロセス中あるいは原稿の種類の判定を受けた後に,投稿論文を取り下げる場合は,取り下げざるを得ない正当な理由を添えて,編集委員長あてに願い出なければならない.
ミスコンダクト
研究上の「ミスコンダクト」とは,「不正行為」とほぼ同義で,捏造(Fabrication),改ざん(Falsification),盗用(Plagiarism)(FFP)を中心とした,研究の遂行上における非倫理的行為を指している.「ミスコンダクト」は不法性,違法性よりも倫理性,道徳性を重視している.
(上記内容は,日本学術会議「科学におけるミスコンダクトの現状と対策-科学者コミュニティの自律に向けて-をもとに一部修正したものである)
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/comment/050831.html
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1031-8.pdf
昨今,研究不正が報道される事態が続いている.看護研究,その中でも人を対象とする臨床研究は,患者やその家族を含む被験者の参加の上に成り立っており,ミスコンダクトがもたらす社会的影響は深刻である.研究の成果は,実践や介入方法を選択する際の判断のためのエビデンスとなることもあり,そのエビデンスが,捏造,改ざんされたものであるとすると,その行為は,患者の健康に対して影響を及ぼす可能性のあるものであり,患者や社会を裏切る行為である.研究者は,データを公正に取り扱い,結果を発表しなければならない.
今日では,電子情報のコピーやペーストがインターネットなどを通じて,容易にできるようになっている.このようなメディア環境であるからこそ,研究者は自分のオリジナルな意見や表現とそれ以外とを明確に区別し,他から得た情報は情報源(文献)を明記するという原則を厳守することが重要になる.
著者は,公表したデータに重大な過誤を発見した場合は,編集委員会にその旨を申し出て,訂正文や撤回文,正誤表またはその他のふさわしい手段を用いて誤りを訂正する必要がある.
- 【事務局】
- 〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-3
- 日本赤十字看護大学内 日本慢性看護学会事務局
- FAX:03-3409-0589